【彼氏持ちの白衣の天使】最強のプリケツ×ブーツが映える超美脚!「緊張します…」と言いながら手マンでよがりまくって潮まで噴いちゃうドスケベちゃん!こんなナースに看病されて???ぇ!(笑) 【初撮り】ネットでAV応募→AV体験撮影 2357
このページには広告リンクが含まれています
※アダルト動画です。未成年者はコチラから退出して下さい。
▼ 画像クリックで無料サンプル動画を表示!

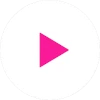
メーカー:シロウトTV
配信日:2025-05-10
出演:瀬下さん 21歳 看護師
内容:「奥が……一番、感じます」 性感帯だという膣奥を指でかき回すたび、彼女は艶やかな黒髪を振り乱して恥ずかしそうに嬌声を上げた。 窓を閉め切ったラブホテルの湿度のせいか白く透き通った肌にはうっすらと汗が滲んでいて、官能的で耽美なギャップが生まれている。気づけば私は無心で彼女の蒸れるわき汗に舌を這わせた。 そして、じんわりと濡れるアソコを更に指で抉った。 彼女とした雑談を思い返し、普段の姿を想像しながら行為に耽るとより一層興奮が増す。 「去年から看護師として都内の病院で働いています」 「彼氏はいます。優しい人。不満は…ないですけど。ちょっと最近、慣れてしまって」 「運動ですか?してないです。日々の仕事が運動って感じですね」 21歳、看護師、彼氏アリ。 ごく普通の日々を、ごく普通に送っている。 そんな彼女が今は同僚にも患者にも見せない痴態を晒している。その事実だけで射精してしまいそうだ。 すらっと伸びた脚にプリっとした美尻、それを引き立たせるようにしっくりと馴染んだ革のブーツが性癖に深く突き刺さった。 触れられること、見られること、愛されること。それらの意味を確かめるように、彼女はこの瞬間に身を委ねていく。 帰り際、彼女を新宿駅まで見送った。 人混みの中、ふたり並んで歩くその時間だけが、妙に現実味を帯びていた。 「今日のこと、彼氏には言うの?」 そう尋ねると、彼女はほんのわずかに、首を横に振った。その仕草は、言葉よりも静かで、強かった。 東改札の奥へと歩いていく後ろ姿。 誰もが行き交う日常の風景に、彼女は静かに紛れていった。
シリーズ:【初撮り】ネットでAV応募→AV体験撮影
「パイパン」「初撮り」の関連動画



































