素人AV体験撮影24
このページには広告リンクが含まれています
※アダルト動画です。未成年者はコチラから退出して下さい。
▼ 画像クリックで無料サンプル動画を表示!

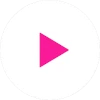
メーカー:シロウトTV
配信日:2010-03-01
出演:りか 25才 お好み焼き屋
内容:りかの働いているお好み焼き屋は老夫婦が個人で経営している小さな店で、りかは言わばそこの「看板娘」だった。昔からの常連客やふらっと立ち寄った一見さんで店はそれなりに繁盛しており、週末になると休日の前祝いと言わんばかりの上機嫌なサラリーマンで席は埋まっていた。そして全ての男性客は、りかの明るく屈託の無い笑顔と、エプロンの上からでもわかる豊満な胸に心奪われていたに違いない。実際、酔った客にセクハラ紛いの冷やかしを受けることなどしょっちゅうで、酷い時には酔っ払ったフリをして胸を触られることもあったが、りかはそれに対し怒ることもなく、いつも笑顔で軽く受け流していた。店内はいつも賑やかで、年老いた経営者夫婦も優しく、たまにエッチな客も含め、りかはその店の全てが好きだった。 しかし、転機は突然訪れる。ある日、店の厨房をほぼ一手に担っていた主人が倒れ救急車で運ばれた。疲労からくる貧血で幸い命に別状は無かったが、倒れた時に右手を強打したらしく全治三ヶ月の大怪我を負っていた。これでは店を開けられない……。りかは食材の仕込みを何度か手伝ったこともあり、その気になれば厨房をできないこともない。しかし、如何せん小さい店でこれ以上人を増やす金銭的な余裕は無く、明らかに人手が足りない。りかでさえこの店が大好きだからこそ、少ない給料でも今まで働いてきたのだ。良案も思い浮かばず、老夫婦が店を畳む相談をしているのを見て、りかは切ない気持ちで胸が引き裂かれそうだった。自分の不甲斐なさに腹が立ち、大好きな店のことを考えるとやるせない思いで頭の中がぐちゃぐちゃになった。 それは不意に口から出た言葉だった。「私……お給料いりません。だから……」 それからりかは必死で働いた。若いアルバイトを二人雇い、自分は奥さんと厨房に立ちながら時折客席の様子を見に行った。自分の分の給料をアルバイト代に当て、自分は余った食材で食費を浮かす。りかの努力のお陰で店の営業は問題なく運び、なんとか主人が戻るまで店を続ける目処は立った。しかし、いくら食に困らないとはいえ、僅かなお金すら得られない状況で生活していくことはできない。体力には自信があったが、自分が店の中心として働いている以上、他所で働く時間などあるわけも無く、すぐに貯金の底が見えてきた。 (短い時間で稼げる仕事なんて……) 途方に暮れるりかの頭に、一人の常連客の顔が浮かんだ。その人はAV業界で働いているらしく、しょっちゅうりかにセクハラ発言をしては周りの苦笑を誘っているような人だった。一度、冗談なのか本気なのか「りかちゃんが出るならギャラ弾んじゃうよぉ☆」なんて言って名刺を渡されたことがある。りかは慌てて財布の中を漁り、一枚の名刺を取り出した。そして、しばらくその名刺を睨みつけた後、おもむろに携帯の番号を押し始めた……。
シリーズ:素人AV体験撮影
「巨乳」「ハメ撮り」の関連動画



































