初々141
このページには広告リンクが含まれています
※アダルト動画です。未成年者はコチラから退出して下さい。
▼ 画像クリックで無料サンプル動画を表示!

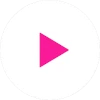
メーカー:シロウトTV
配信日:2010-11-01
出演:純奈 24歳 家事手伝い
内容:健康器具は私の心の支えなんです。そう元気そうに語る「純奈」(24)。純奈が健康器具にハマってしまったのは小学生の頃。父親が毎日使っていた電気マッサージ器を股間に当て出したことが全ての始まりだった。毎夜気持よさそうに電気マッサージ器を肩に当ててる父の姿を見て、子供心に「私もやってみたいなぁ」という素朴な感想を抱いたのだ。しかし、父に「電マを貸してくれ」と頼んでも、まったく貸してなかった。毎夜頼み込む私の姿を見て、なぜか父は電マを隠すようになってしまった。隠されると何故か逆にもっと電マへの憧れが強くなり、父がいない昼に父の書斎を探すことが彼女の日課になった。そんな日々を過ごすこと4日目、ついに彼女は念願の電マを探し当てることができた。そして緊張の一瞬、恐る恐る電マを肩に当ててみた。・・・しかし、くすぐったいばっかりで、まったく気持よくなかったのだ。父の毎夜のあの気持よさそうな至福の顔になんてまったくなれなかったのだ。それにがっかりしてしまった彼女はその瞬間から電マへの興味をまったく失ってしまった。そしてその電マを投げ捨てた。未だ「ブンブーン」と唸りを上げる電マ。電マに失望した彼女。そんな人間と健康器具の微妙な時間が10分程流れていた。それはまるで別れ話を切り出す前の熟年カップルが醸しだす時間のようであった。しかし彼女はそんなことはお構いなしだった。彼女の電マに寄せていた希望や、夢。それら全てが裏切られたのだから。絶望に打ちひしがれながらも、彼女はまだ電マに可能性を見出そうとした。そしてカラダの他の部位に宛てがうという考えに至った。最初は胸、腰、そしてお腹辺りに当てたとき、彼女のカラダが今まで感じたことのない疼きみたいなものが生まれた。そしてそのまま下の方に動かすと、それはもう今まで感じたことのない快楽を感じることができたのだ。その刺激の虜になってしまった彼女はそれから一時間もの間、電マを股間に押し付け続けた。これが電マの虜、いや、電マの奴隷とも言えるであろう存在の誕生だったのだ。それからというもの親の目を盗んでは電マを当て続け、そして毎回のように快楽の魅力に取り憑かれていった。雨の日も、風の日も、入学式のときも、誕生日も、好きな男の子ができたときでも、つらいことがあったときでも。彼女は電マという健康器具を常に心の支えとして生きてきたのだ。
シリーズ:初々
「ハメ撮り」「美乳」の関連動画



































